こどもの視力
こどもはものが見えにくくても、それをなかなか上手に伝えることができません。こどもの成長にとって、とても大切な視力です。いつも注意深く見守ってあげましょう
こどもは学習の約80%を目からの情報にたよっています
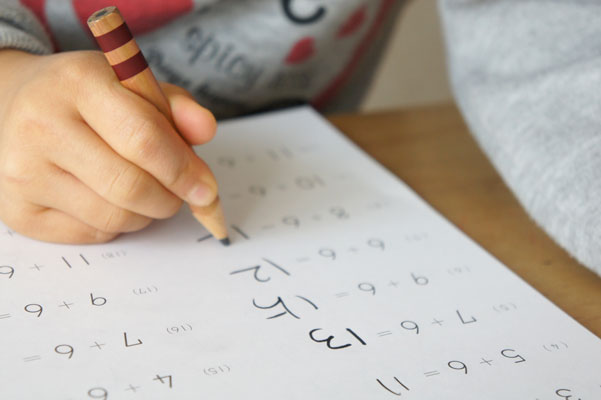
こどもの視力は、生まれてからものを見るという自然の訓練を通して、徐々に発達し、およそ6歳ごろまでに完成されます。もしこの時期に視力に問題があることに気づかずに放置しておくと、運動や学習をする上で大切な思考力、推測力、想像力の発達を妨げることにもなりかねません。こどもにとっての視力は、心身ともに健康な成長をとげるための大切な窓口です。 日常のちょっとしたしぐさに注意を払う、それが視力保護の第一歩と言えます
日頃から、お子さまの目つき、姿勢、態度などに気をつけるとともに、専門家による視力測定も定期的にうけられることをおすすめします
こんなこと、ありませんか
チェックしましょう。こんなしぐさや症状は、視力の問題からくる影響が考えられます
- 見るとき
- 目を細める
- 片目をつぶって見る
- 頭を回し、横目で見る
- 頭を傾けて見る
- あごを引いたり、上げたりして見る
- 学習・あそび
- おちつきがない
- あきっぽく、根気がない
- 集中できない
- 目の様子
- 目をよくこする
- 目をパチパチさせる
- 視線が内や外、上や下にずれることがある
- 涙をよく流す
- 明るい戸外でまぶしがる
- 生活
- テレビを近くで見たがる
- よくつまづく、転ぶ
- ひんぱんに頭痛をうったえる
- 家族
- 両親・兄弟姉妹も視力が悪い
大切な目を守るために
こどもの目の健康のために、気をつけてあげたいこと
- 健康づくり
- 食べ物の好き嫌いをなくし、バランスのとれた食事をとりましょう
- 規則正しい生活をおくり、睡眠時間もじゅうぶんにとりましょう
- 戸外での運動やあそびで、総合的な体力づくりをしましょう

- 勉強・読書
- 目と文字の距離は30cm以上離し、正しい姿勢で
- 机やイスは、身体に合ったものを選びましょう
- 寝ながら、本を読まないようにしましょう
- 目を細めて見ないようにしましょう

- テレビ等
- テレビは明るい部屋で2m以上離れて見ましょう
- 調整された鮮明な画像で見ましょう
- 1時間見たら、10分間ぐらい目を休めましょう
- テレビゲームは30分間をめどに休憩をとりましょう

- 照明
- 部屋全体を明るくし、デスクスタンドを併用しましょう
- スタンド照明は、鉛筆をもつ手と反対側の横に置き、直接光が目に入らないようにしましょう

お子さまの視力保護を育児のひとつとお考えください
視力は6歳ごろまでに完成されます
生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、明暗がわかる程度ですが、生後6ヶ月を過ぎると外界のものが一応見えるようになります。そして、身体の成長とともに視力も徐々に発達していき、6歳ぐらいになると大人と同じような視力になります
- 生後1ヶ月
- 目の前の手の動きがわかる
- 3ヶ月
- 視力 0.01~0.02
- 6ヶ月
- 視力 0.04~0.08
- 1歳
- 視力 0.2~0.25
- 2歳
- 視力 0.5~0.6
- 3歳
- 視力 0.8
- 4~5歳
- 視力 1.0
- 6歳
- 視力 1.0~1.2
こども専用のメガネを選びましょう
こどものメガネは、機能性、デザイン、安全性、かけ心地などにも気を配って、こどもの顔にぴったり合ったメガネを選んであげましょう。またこどもは動きが活発なため、メガネの正しい位置がずれたりして、耳や鼻が痛くなったりすることがありますので、つねにメガネの状態に気をつけ、お店で調整をしてもらいましょう
※お子さまのために、ご家族がメガネ嫌いにならないようにしましょう
学校の視力検査
学校では視力をA〜Dの4ランクで評価します。お子さまの視力がBランクやCランクでも、近視とは限りません。乱視や弱視の場合もあり、遠視でも度数によっては視力が低くなります
- A(1.0以上)
- 教室の一番後ろの席からでも黒板の文字を楽に読めます。通常はメガネはいらないと考えられます
- B(0.7-0.9)
- 教室の後ろの席でも黒板の文字をほとんど読めますが、小さい文字になると見えにくいものがあります。状況によってはメガネを使用してもよいでしょう
- C(0.3-0.6)
- 教室の前の席であれば何とか見えていますが、きれいに見えているのは黒板全体の半分くらいです。眼を細くして黒板を見ている可能性があります。メガネを考えてもよい時期です
- D(0.2以下)
- 一番前の席でも黒板の字は読めません。本人が見えているから大丈夫といっても、実際には読めていないと考えられます
